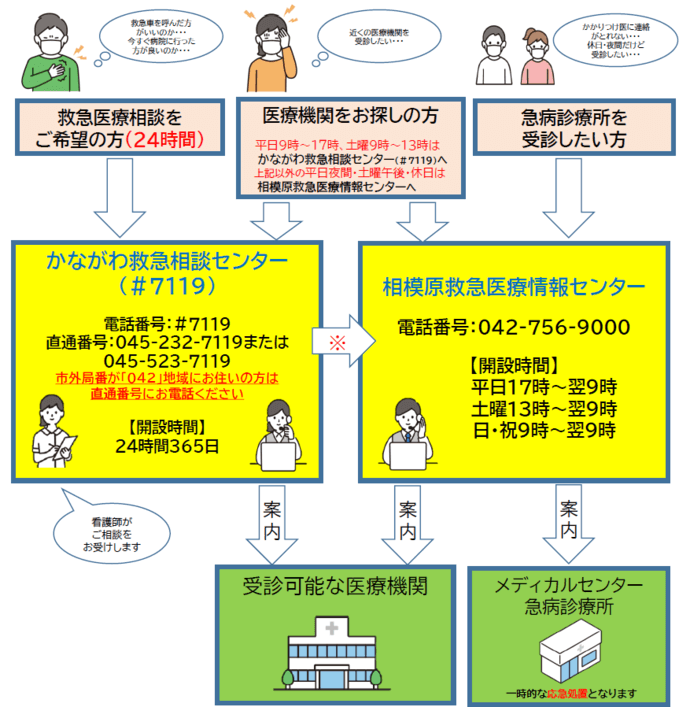ブログ


横山地区から広げる「自助・共助・公助」 ――災害時のくすりと横山Kizunaパーキングのこれから
地区ごとの平時からの関係作りと災害時の医療介護を考える。
横山から広げる「自助・共助・公助」
――災害時のくすりと横山Kizunaパーキングのこれから
⸻
横山で「災害」と「絆」を語り合いました。
相模原市中央区でさがみはらファミリークリニックを立ち上げてから12年、在宅医療や訪問診療を通して地域とかかわってきました。
水上は災害が起きた際に、県の災害医療コーディネーターの研修を終了しており、本部等での役割を担います(関連ブログはこちら)
今回、横山地区の皆さんと一緒に、
• 災害時のくすりの確保
• 必要な情報をどう届けるか
• 住民同士・専門職同士の「顔の見える関係づくり」
• 横山発の取り組み「横山Kizunaパーキング」の今後
について、グループワークと全体討論を行いました。
⸻
災害時のくすりをどう確保するか
まず話題になったのが「災害時のくすり」です。
• 慢性疾患の内服薬(血圧・コレステロールなど)は、自分の分は自分で確保することが大原則
• 可能であれば、1〜2週間分を多めに処方してもらい、ローリングストックしておく
• 自宅には昔の「薬箱」のイメージで、
• 解熱鎮痛薬
• かぜ薬
• 必要に応じて胃腸薬や貼り薬
などの市販薬を、家族で共有しておく
施設や事業所からは、
• 「緊急時用のお薬ボックス」を準備しておき、
• 地域の方が本当に困ったときには、医師の確認のもと、解熱剤や痛み止めをお渡しできる仕組みがあると安心。
といった意見も出ました。
「誰に優先して薬を渡すか」という視点も重要で、
命に直結する薬が必要な方をどう見える化するか――今後の課題として共有されました。
⸻
情報をどう届けるか ― 特に認知症の方への配慮
2つ目のテーマは「災害時の情報提供」です。
• 認知症の方や、
自分の名前・家族・連絡先がすぐに言えない方の情報を、誰が・どこで把握しておくのか
• ケアマネジャーがすぐ動けない場合、支援の手が届きにくくなる
という現場の実感が出されました。
かつて冷蔵庫の中に「お薬情報などを入れた筒」を保管する取り組みがありましたが、
• 中身が古いまま更新されていない
• そもそも存在を忘れている方も多い
という話もあり、もう一度、地域で周知し直し、内容を見直す必要があるという意見で一致しました。
また、
• 指定避難所は知っていても、「そこまでどうやって行くか」が決まっていない
• 福祉用具事業所などと連携して、車いすや移動手段をどう確保するか
といった、“行ける避難所”にするための仕組みづくりも話し合われました。
⸻
日ごろからの「顔の見える関係づくり」
3つ目のテーマは、「従事者と住民の顔の見える関係づくり」です。
• 初回契約やサービス利用開始のタイミングで、
• 緊急時の連絡先
• 避難場所
• 家族構成
などを一緒に確認しておく
• お茶のみ話の中で、さりげなく災害の話題を出し、
情報がどこにあるかを一緒に整理しておく
• 家族にも、薬の飲み方や避難時の動き方を共有しておく
こうした日常のコミュニケーションの積み重ねが、
「いざという時に誰一人取り残さない」ための土台になると、改めて確認できました。
⸻
横山発「Kizunaパーキング」のこれから
以前にご紹介した横山Kizunaパーキング🅿️についてのブログはこちら!
後半は、横山地区発の取り組みである**「横山Kizunaパーキング」**についての意見交換でした。
Kizunaパーキングは、
• 医療・介護・福祉の専門職が、
地域の狭い道や個人宅を訪問するときに使える「地域で支え合う駐車スペース」
• 違法駐車を避けつつ、在宅医療や訪問介護を支える仕組み
としてスタートした取り組みです。
今回は、
• 市の助成金を活用して、新しいピンク色の看板を整備すること
• ベンチと組み合わせて、
• 情報発信の場
• ウォーキングラリーなどの「地域のランドマーク」
としても活用していくこと
• 駐車場マップをA3版で作り直し、
必要な事業所や関係者に配布していくこと
などが共有されました。
看板にはQRコードも付けて、
• 駐車場所の情報
• 地図へのリンク
などをわかりやすく伝えていく構想も出ています。
横山から始まったこのモデルは、すでに他地区にも広がり始めており、
来年の市内社会福祉協議会の報告会でも、横山地区が代表事例として発表予定とのことです。
⸻
おわりに ―
「横山から、誰一人取り残さない地域へ」
コロナ禍を経て、なかなか顔を合わせての会議が難しい時期もありましたが、
久しぶりに多職種と住民が一堂に会し、
「自助」「共助」「公助」をどうつないでいくかを真剣に話し合う貴重な時間になりました。
• 災害時のくすりの備え
• 情報の見える化
• 顔の見える関係づくり
• 横山絆パーキングを軸とした地域の支え合い
どれも、一度決めて終わりではなく、
これからも少しずつアップデートしていくテーマです。
横山から始まったこの取り組みが、
「誰一人取り残されないまちづくり」の一歩として、
市内全域にも広がっていくことを願いながら、
在宅医として、また一人の地域住民として、今後も関わっていきたいと思います。
医療法人社団はやぶさ
さがみはらファミリークリニック 理事長
みずじゅんクリニック 院長
水上潤哉